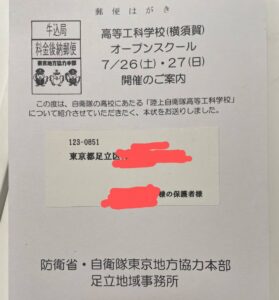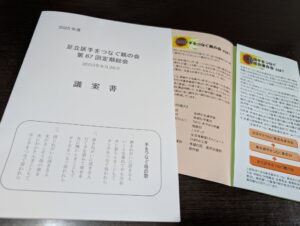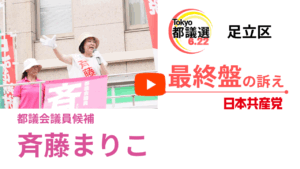コロナ禍でのバス利用の減少によって、バスの減便が一気にひろがりました。都民のかけがえのない生活・移動手段を守るため、今こそ東京都が支援にふみだすときと求めました(2022年3月16日、公営企業委員会)。
コロナで厳しいなか、公共交通の役割と現状は
〇斉藤委員 最後のテーマですけれども、公共交通の在り方について伺います。
コロナ禍での自粛やテレワークの普及によって都民の行動変容が起こり、交通局での経営は厳しい環境になっています。都営地下鉄は、コロナ以前と比較して、二〇二〇年度の乗客者数は三割程度の減、そして、都営バスも二割減で推移しているということが、経営計画案の中でも示されています。今後は、コロナ以前と比較して、地下鉄は一五%程度、その他の事業は一〇%程度減少が続くという想定で、料金収入は厳しい状況が続くということになります。
しかし、そうした中でも、都民の移動の保障をしていかなくてはならないのが、公共交通を担う交通局の役割だと考えますが、まず見解を伺います。
◯神永企画担当部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 安全・安心の確保を最優先に、質の高いサービスを提供し、東京の都市活動や都民生活を支え続けていくことが都営交通の果たすべき役割と考えております。
交通局では、こうした考えの下、これまでも事業運営を行っており、新たに策定する経営計画でも、地下鉄全駅でのホームドア整備やバリアフリールートの充実に取り組むほか、バス停留所の上屋、ベンチの整備を進めるなど、厳しい経営状況にあっても、必要な事業を着実に実施していくこととしております。
◯斉藤委員 都市活動や都民生活を支え続けていくことが都営交通の果たすべき役割と認識しているということで、重要な視点だと思います。今後も忘れてはならない認識だというふうに思います。
バス路線の現状について伺います。
今年度、バスの路線を廃止したり、減便したりした路線は幾つあるでしょうか。
◯太田バス事業経営改善担当部長 都営バスではこれまでも、地域のニーズや需要の変化をきめ細かく把握し、代替交通の有無などの路線特性を踏まえまして、毎年定期的に路線の新設、廃止、増便、減便などの見直しを行っているところであります。
今年度は、廃止した路線はございませんが、昨今のご利用の減少等を踏まえましてダイヤを改正しておりまして、平日、土曜、休日ダイヤのいずれかで一便だけ減少したものも含めますと、計十八路線が減便となりました。
実施に当たりましては、お客様の利便性に最大限配慮いたしまして、影響をできる限り抑えるため、このほとんどについて、ご利用が多い時間帯の運行間隔を変えずに維持するか、あるいは、拡大しても三分程度にとどめております。
◯斉藤委員 今年度廃止した路線はないということですけれども、土日や休日ダイヤ、減便をしたということも含めると、全部で十八路線で減便があるということです。減便する路線については、ほかに代替路線や代替交通があるところや、減らした時間帯についても、極力影響が出ない範囲で選んでいるということも伺いました。
しかし、私たちは、都民の移動の権利を保障するためにも、バス路線の廃止は極力行うべきではないと考えています。特にバスは、高齢者にとっても乗りやすい交通機関であり、高齢者を含めた住民の交通権、移動する権利を保障することは、公共交通、とりわけ自治体の重要な役割です。だからこそ、都として公共交通を維持することが求められています。
今こそバス路線へのサポートにふみだすとき
〇斉藤委員 そこで伺いますが、交通局への一般会計の繰入れの項目と額、その根拠について伺います。
◯土岐次長 地方公営企業は、独立採算制により経営を行うことが原則とされておりますが、一部の経費につきましては、法令等の定めにより、一般会計が負担しております。
交通局では、基礎年金拠出金に係る公的負担分に対する補助金、シルバーパス等の料金減免措置に対する補填金、高速電車事業の建設改良に対する出資金などが、一般会計の負担として繰り入れられており、令和四年度予算における繰入金額は、交通局所管の三会計合計で三百十四億円でございます。
◯斉藤委員 シルバーパス等の料金減免措置に対する補填金、これはまさに高齢者の移動を保障し、社会参加や健康維持につながる福祉的要素が強いものです。また、高速電車事業の建設には、多額の予算が必要になりますが、独立採算では担えないものでも、公営企業法に基づいて、都民にとって不可欠な公共交通の整備に都が費用を負担しているというものです。一方で、都営交通の運行維持に対しては、独立採算の原則で、現時点で都からの補助はありません。
私は、コロナ禍で厳しい今こそ、この在り方を見直すべきではないかというふうに考えています。都の地域公共交通計画の策定に向けて地域公共交通の在り方検討会が開かれてきましたが、この中の議論を見ると、地域公共交通が置かれている現状がよく分かります。例えば、バス事業者は非常に厳しい経営状況にある、自治体としてのサポートについて検討していただきたいという声や、具体的に、生活路線の確保、維持に対する支援を検討してほしい、また、都や区市町村の役割に支援という意味合いを込めていただけるとありがたい、こういう切実な声が上がっています。
交通の一事業者として、交通局にも共通する思いがあるのではないかと思いますが、いかがですか。
◯太田バス事業経営改善担当部長 お話の検討会には、交通局も、バス事業者としての立場から委員として参画しております。
交通局からは、事業運営上抱えている課題などについて情報提供を行いますとともに、行政の支援の在り方等についても意見を述べてきたところでございまして、これらを受け、昨年十二月に、地域公共交通の基本方針の中間のまとめが公表されたところであります。
この中で、都は地域公共交通の充実等に向けた促進策の構築などを実施するとともに、区市町村は生活交通の充実等に資する取組を推進するなど、都や区市町村の役割を示しながら様々な支援に言及しておりまして、交通事業者としての意見が反映されているものと考えております。
◯斉藤委員 交通局もこの検討会に参加して、事業運営上の課題など情報提供したほか、行政の支援の在り方等についても意見を述べてきたということで、重要なことだと思います。
しかし、この地域公共交通計画の案を見てみても、具体的な支援の言及があるわけではなくて、まだまだ都の取組の弱さを感じますが、しかし、こうした議論が事業者から上がっているということは重要なことだというふうに思います。
在り方検討会の議論では、こういう発言もありました。現場では、財源確保が課題であり、そのための制度制定は重要である、公共交通は、今まで民間事業として捉えられてきたが、高齢化や人口減少の進行もあり、福祉的な視点からの対応も求められている。
重要な指摘だと思いますが、交通局の見解を伺います。
◯太田バス事業経営改善担当部長 路線バスは、通勤通学や買物、高齢者の通院など、地域の暮らしを支える身近な移動手段であり、各事業者におきましても、地域に必要な路線については、赤字路線であっても黒字路線の収益で支える総合的な事業運営を行うことで維持してまいりました。
一方、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、各事業者とも乗車人員は大きく落ち込んでおりまして、検討会において、東京バス協会からは、これまでのような路線網の維持は困難となっているため、都としての財政的な支援が必要といった意見が出ております。
交通局といたしましても、財政面などの行政の支援の在り方等について意見を述べてきたところであります。
◯斉藤委員 検討会で、東京バス協会から、これまでのような路線網の維持は困難で、都の財政的な支援が必要だという意見が出ているということ、また、交通局も、財政支援などの行政の支援の在り方について意見を述べてきたということはとても貴重なことだというふうに思います。
民営化からの転換をすすめる欧州の経験にも学んで
〇斉藤委員 日本では、長らく公共交通の民営化が進められ、その下で、採算が取れない路線は廃止され、困難な地域ほど切り捨てられるということが続いてきました。
しかし、一度は民営化が進んだヨーロッパでも、今では、交通は公的に支えるものという認識が確立しています。欧米の公共交通は、税金や補助金を原資とした運営が一般的になり、さらに無料化に進む自治体が増えています。フランスでは、交通権という言葉が法律の中で明文化され、行政が目指すべき交通政策の指針とされているということ、また、地域交通全体が、社会インフラとして必要なことであるから、不採算の面があっても行政が実施しなければならないとされている、そういうことが、自治体国際化協会のパリ事務所の報告にも示されております。
交通局としても、民間の手法や論理だけでは成り立たないのが公共交通だという立場に立って、都民の交通を守り、関係各局と認識を共有し、連携をしていくことが必要だと思いますが、いかがですか。
◯神永企画担当部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 地方公営企業は、独立採算制の原則に基づき、企業としての効率的な経営を図りながら、質の高いサービスを提供し、地域住民の公共の福祉を増進するよう運営することとされております。
このため、新たに策定する経営計画の下、安定した輸送サービスを提供していくために、経費の縮減や収益力の強化はもとより、業務の在り方や執行体制の構造の見直しに取り組んでまいります。
なお、関係各局とはこれまでも、事業の推進に当たり、課題や認識を共有するとともに、様々な面で連携を図ってきたところであります。
今後も、適切な事業運営に努めてまいります。
◯斉藤委員 最近でも、弱肉強食の新自由主義の政策の柱として、一九八〇年代のイギリスの保守党のサッチャー首相が進めてきた鉄道の民営化が破綻し、再国有化の見直しが進み、不採算で廃止された路線も一部復活するということも報道されています。
独立採算だけで効率化を進めようとすれば、不採算路線や事業が切り捨てられ、都民の移動の保障が行えなくなるのが交通事業です。世界に目を転じれば、新しく当たり前の公共交通の考え方が既に広がっています。コロナの影響により公共交通を取り巻く状況が大きく変わり、各事業者とも、従来の独立採算の考え方だけでは維持ができない、こういうことが浮き彫りになった今、一般会計も含めて、公的にしっかり支えていくという公共交通の在り方を検討していくべきときだというふうに思います。
ぜひ、関係各局と課題や認識の共有を行い、公共交通を守る役割を果たすことを求めて、質問を終わります。